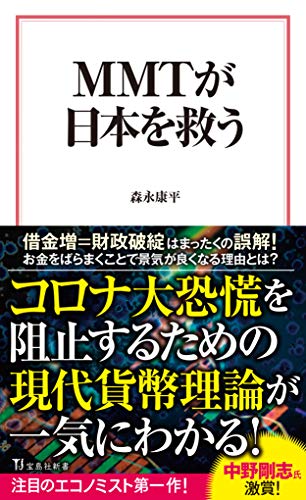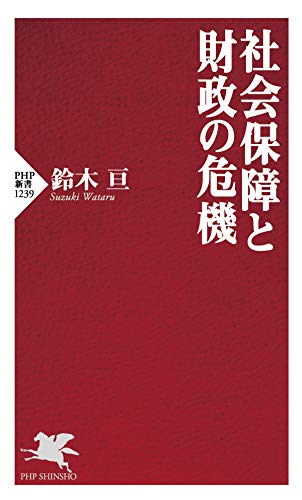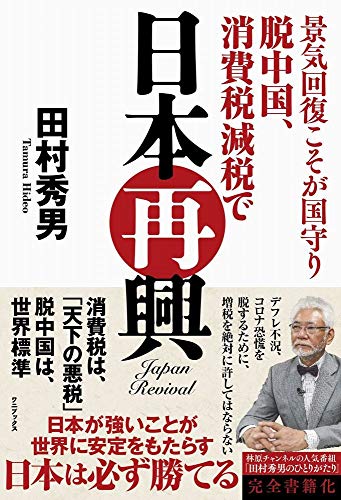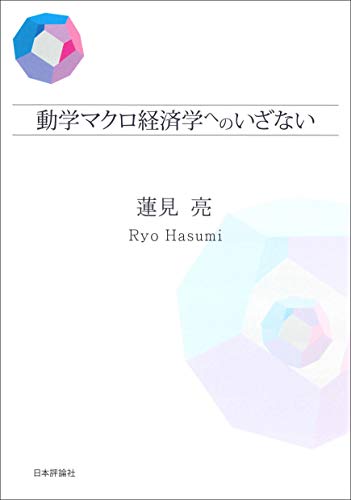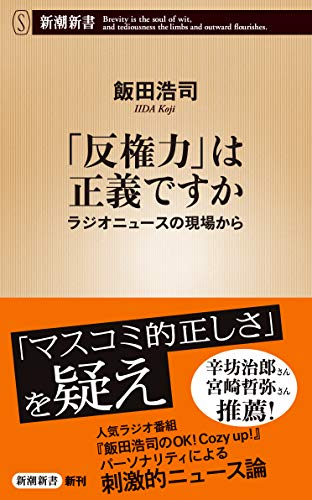明けましておめでとうございます。今年も皆さんのご多幸、ご健勝をお祈りしております。
毎年恒例の経済書ベスト20も、今回で8回目(9年目)を迎えました。ネット(twitter、Facebook、田中宛メールなど)を経由して、今年は100名以上の方々から投票を頂きました。参加いただいたこと、また拡散頂戴したこと感謝申し上げます。昨年は新型コロナ危機という史上でもまれな国難の中で、皆さんがどのような問題意識でどんな本を読まれたのか、とても気になっていました。また何度か、今回はとりやめようかとも思いましたが、やはりこの重要な年を記録する上でもこのイベントも意義があるのではないか、と思い直し、皆さんのご協力のもと実行できましたこと、ここに何度も感謝いたします。ありがとうございます。
今回も2020年1月から20年12月までに出版された経済書の中から、例年の基本三冊から変更して5冊をあげ、ハッシュタグをつけて選んでいただきました。
おひとりの投票ポイントは、今回から総計15ポイントになります。1位に5点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。順位が不明のものなどは私の方で適宜配分しています(例:順位不明で2~3作品投票は、各著作に4点ずつの配分。1作品だけ投票の場合は5点を付与など。また順位不明でも明らかに順位づけをしている旨が読み取れるときはそれを考慮。順位が完全に不明で4作品以上あるときは、3点づつ付与)。
『エコノミスト』(毎日新聞社)やダイヤモンド社のような雑誌側の選んだ専門家たちの選択よりも、ネットを通じて多数の方に自由に投票していただいた結果は、価値のあるものと思っています。
昨年までの一位をご紹介します。
2012年第一位 ポール・クルーグマン
『さっさと不況を終わらせろ』(早川書房)
2013年第一位 田中秀臣編著
『日本経済は復活するか』(藤原書店)
2014年 実施せず
2015年 原田泰
『ベーシックインカム』(中公新書)
2016年 井上智洋
『ヘリコプターマネー』(日本経済新聞社)
2017年 飯田泰之
『マクロ経済学の核心』(光文社新書)
2018年 田中秀臣
『増税亡者を名指しで糺す!』(悟空出版)
2019年 柿埜真吾
『ミルトン・フリードマンの日本経済論』(PHP新書)
では、今年の第一位をご紹介します! ついに無冠の帝王が初の一位です!
『日本経済再起動』(かや書房)獲得ポイント293


著者から投票してくださった皆様へ
著者を代表して、高橋洋一さんより。
明けましておめでとうございます。
『日本経済再起動』(かや書房)が、経済書ランキング投票で第一位になったということで、これもおめでたいことです。
この本は、田中秀臣さんとの共著です。そして、経済書ランキング投票の運営者は田中さんですから、何か裏があると勘違いしそうですが、某国のボス選びではないので、それはないと断言できます(笑)。
この本は、コロナ禍の中、田中さんとオンライン対談したものです。私は、オンライン時間の直前にテレビ出演などがあり、帰宅途中のタクシー内からオンライン対談をしたこともあるのですが、いつも綱渡りでした。でも、オンラインで時間の制約が緩くなったので助かりました。
本の中身は、なんといっても、あの「MMT」を批判していることが特徴です。リフレとMMTは似て非なるものですが、その点はこれまで簡単に紹介してきましたものを本の形でまとめてみました。それには、共著者の田中さんに大変丁寧な資料を作ってもらいました。簡単に言えば、リフレでは数本のモデル式があるのに対し、MMTではそのうちの1本しかなく、しかもその解釈は恣意的です。これでは、似て非なるものにあるのは当然です。
リフレは、バーナンキやクルーグマンらの考え方と同じですが、MMTを彼らは否定します。一般の方には、その差がわかりにくいと思いますが、この本ではその点を対談の形で丁寧に説明しています。これを含めて、本書は多くの著名人にも読んでもらいました。
対談はコロナ禍に行われたので、現実には編集者を含めて一度も対面してません。ポストコロナはそういう時代でしょう。
それにしても、本の現物を見たとき、表紙は笑ってしまいました。表紙は、菅首相、田中さんと筆者の顔写真があるのですが、三人とも「明るい」のです。菅首相は、「日本を明るくする会」の名誉総裁だし、田中さんは立派に明るくしているし、筆者もその仲間であることを自覚しています。
本書は紀伊國屋書店で実売されたが、1Fと3Fに置かれ2Fでなかったので、書店側もこの本の「趣旨」をわかっていたのかと苦笑してしまいました。
第二位 三浦春馬
『日本製』(ワニブックス)獲得ポイント155
「僕達も人間だから、モチベーションを高く保ち続けることが難しい時期もあるかもしれません。でも、そういった時にも携わった作品……映画や舞台、ドラマであったり、この書籍や写真集といったものが誰かの気持ちに繋がって、社会貢献のきっかけになるかもしれない。そういうふうに思えれば、弱っている時期も頑張っていけるというか、自分のやっていることがちょっとした着火剤になりえると考えられる健康的なマインドを持ち合わせていたいとすごく思うんですよね。『日本製』では、そういったことをたくさん教えてもらえましたし充実したいい時間、いい心の持ちようを教わってきた四年間だったと思います」『日本製』388頁より引用。
第三位 上念司
『経済で読み解く日本史 平成時代』(飛鳥新社)獲得ポイント117

著者から投票してくださった皆様へ
経済で読み解く日本史平成時代をお読みいただいた皆様ありがとうございました。この本はシリーズ6巻の中で一番ページ数が多いのですが、おそらく一番速く読める一冊だったのではないでしょうか?
お読みいただければ分かる通り、この本は私たちがリアルタイムで生きてきた平成という時代の日記みたいなものです。随所に私のあまり影響を与えられなかった活動なども書いておきました。思えば私が田中先生に出会ったのも平成16年(2004)のことでした。
あれから20年近く時が流れ、もうリフレ政策も政府・日銀の政策として取り込まれるようになったのは隔世の感ですね。
とはいえ、去年のコロナショックで日本経済は別の意味で窮地に追い込まれております。令和になっても平成が続いているかのような、、、うーんイマイチ。
でも、正しい経済学の知見があればきっとこの難局も乗り越えることができるでしょう。私も名誉棄損で訴えられたり散々な目に遭いましたが決してあきらめることなく頑張ります!w
第四位 森永康平
『MMTが日本を救う』(宝島社新書)獲得ポイント46

著者から投票してくださった皆様へ
この度は錚々たる方々が受賞者として名を連ねる本賞のなかで、拙著が第4位に選ばれたことは身に余る光栄です。企画を主催されている田中先生、ならびにご投票いただいた皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。2017年には父の本も選出いただいたようで、親子で受賞するのは初のことかもしれません(笑)経済政策についてはリフレ派やMMTerなど支持する考え方は様々ですが、いずれも最終的な目的は日本経済を再び力強いものへと変えていくことかと思います。「失われた30年」しか知らない私ですが、少しでも日本経済の回復に貢献できるよう、2021年も精進していきたいと思います。改めて、ありがとうございました。
第五位 鈴木亘

著者から投票してくださった皆様へ
拙著『社会保障と財政危機』(PHP新書)にご投票いただき誠にありがとうございます。年末近く(11月13日)になって出版したにもかかわらず、このように高くご評価を頂いたことに、深く感謝申し上げます。
本書は、コロナ禍の中、雇用や生活保護、医療、介護、年金などの社会保障制度がどのような状態に陥っているのか、どうすれば問題解決できるのか、現状と対策を詳しく論じたものです。社会保障の各分野とも、危機的な状況もしくは危機が迫っている状態にありますが、それらは全く新しい問題というよりは、これまで先送りされ続けてきた構造的問題が、コロナ禍という状況の中で限界に達しつつあるのだというのが本書の見立てです。したがって、本書の基本的なメッセージは、このような危機下であるからこそ、抜本改革に着手するのが結局は解決のための一番の近道だというものです。
一言でいえば、「ピンチはチャンス」ということですが、これは社会保障のみならず、コロナ禍で苦しんでいる他の多くの分野に当てはまることだと思います。2021年こそ、反転攻勢に打って出て、「災い転じて福」となしましょう! 皆様にとって2021年が飛躍の年になることを心より願っております。
第六位 渡瀬裕哉
『税金下げろ、規制をなくせ~日本経済復活の処方箋~』(光文社新書)獲得ポイント35

著者から投票してくださった皆様へ
皆様からの貴重な一票ありがとうございました。本書は経済書というよりは政治運動の本としての性格が強く、市井の一国民が政治経済に影響を与えるための処方箋をまとめたものです。それにも関わらず、高名な経済学者の先生方の著書と並んでご紹介頂けることに感謝いたします。現在の日本でも巷で取り沙汰される経済政策には様々な主張がありますが、大半の国民は議論の成り行きを見ているだけで、その実行に実際に関与できるわけではありません。しかし、本当は民主主義を機能させることで、誰もが望まない増税を回避し、減税を実現していくことができるのです。本書の元ネタは米国共和党保守派の減税運動であり、日本の有権者は海外の政治に学ぶところがまだ多くあると考えております。知行合一の精神を大切にし、今後とも国民の皆様にアイディアをお伝えできれば幸いです。
第七位 ポール・クルーグマン
『ゾンビとの論争』(早川書房)獲得ポイント29

著者から投票してくださった皆様へ(訳者・後書きの山形浩生さんからのコメント)
2020年ベストにランクインしたのは光栄しごくながら、訳者として本書には大変に複雑な気持ちを抱いているのは事実ではあります。緊縮財政イデオロギー批判、財政金融の引き締めイデオロギー罵倒は納得いくものではありますが、その数倍にものぼる、すべては共和党が悪い議論、ましてそれが数十年前から続いてきた長年の共和党世界支配のシナリオに基づくのだという、あからさまきわまる陰謀論は、このぼくですらドン引きで、それが正しいにしてもアメリカのローカルねたでしかなく、我々日本人にとっては対岸の火事という……が、政権がかわってこの先のクルーグマンの論調はどうなるのか、楽しみではありますし、またそれを紹介できる日がくるのを楽しみにしております!
『絶望を希望に変える経済学』(日本経済新聞社)獲得ポイント28
第九位 高橋洋一
『明解 経済理論入門』(あさ出版)獲得ポイント23
第十位 ステファニー ケルトン
第11位 鎌田雄一郎
『16歳からの初めてのゲーム理論』(ダイヤモンド社)獲得ポイント14
第12位 高橋洋一
『コロナ大不況後、日本は必ず復活する 』(宝島社)獲得ポイント12
第13位 野口旭
『経済政策形成の論理と現実』(専修大学出版局)獲得ポイント11
第14位 高橋洋一
『高橋洋一、安倍政権を叱る! 』(悟空出版)獲得ポイント10
第14位 田村秀男
『日本再興』(ワニブックス)獲得ポイント10
第16位 チャールズ・マンスキー
『データ分析と意思決定理論』(ダイヤモンド社)獲得ポイント9
第17位 坂井豊貴&オークション・ラボ
『メカニズムデザインで勝つ ミクロ経済学のビジネス活用』(日本経済新聞出版)獲得ポイント8
第17位 斎藤幸平
『経済の論点がこれ1冊でわかる 教養のための経済学 超ブックガイド88』(亜紀書房)獲得ポイント8
第20位 吉田敦
『アフリカ経済の真実 ――資源開発と紛争の論理』(ちくま新書)獲得ポイント7
第20位 蓮見亮
『動学マクロ経済学へのいざない』(日本評論社)獲得ポイント7
第20位 飯田浩司
『「反権力」は正義ですか―ラジオニュースの現場から―』(新潮新書)獲得ポイント7
(特例17位相当) ジョセフ E スティグリッツ
『プログレッシブ キャピタリズム』(東洋経済新報社)獲得ポイント8
『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』など昨年ランキングに入って今年も票を複数獲得(獲得ポイント8)しましたが除外しました。またスティグリッツ 『プログレッシブ キャピタリズム』は、投票対象期間外に出されてますが(奥付は19年12月20日)、複数投票を得ていること、あまりに年末での出版なのでそれも考慮して特別枠として掲示しました。ご理解ください。来年以降はこの点(予想外に年末に出た著作)もなんらか対応していきたいと思います。
その他を含めて投票獲得著作数は、全94著作になります。
本当に今年もありがとうございました!
今年一年の皆様のご多幸とご健康をお祈りしております!